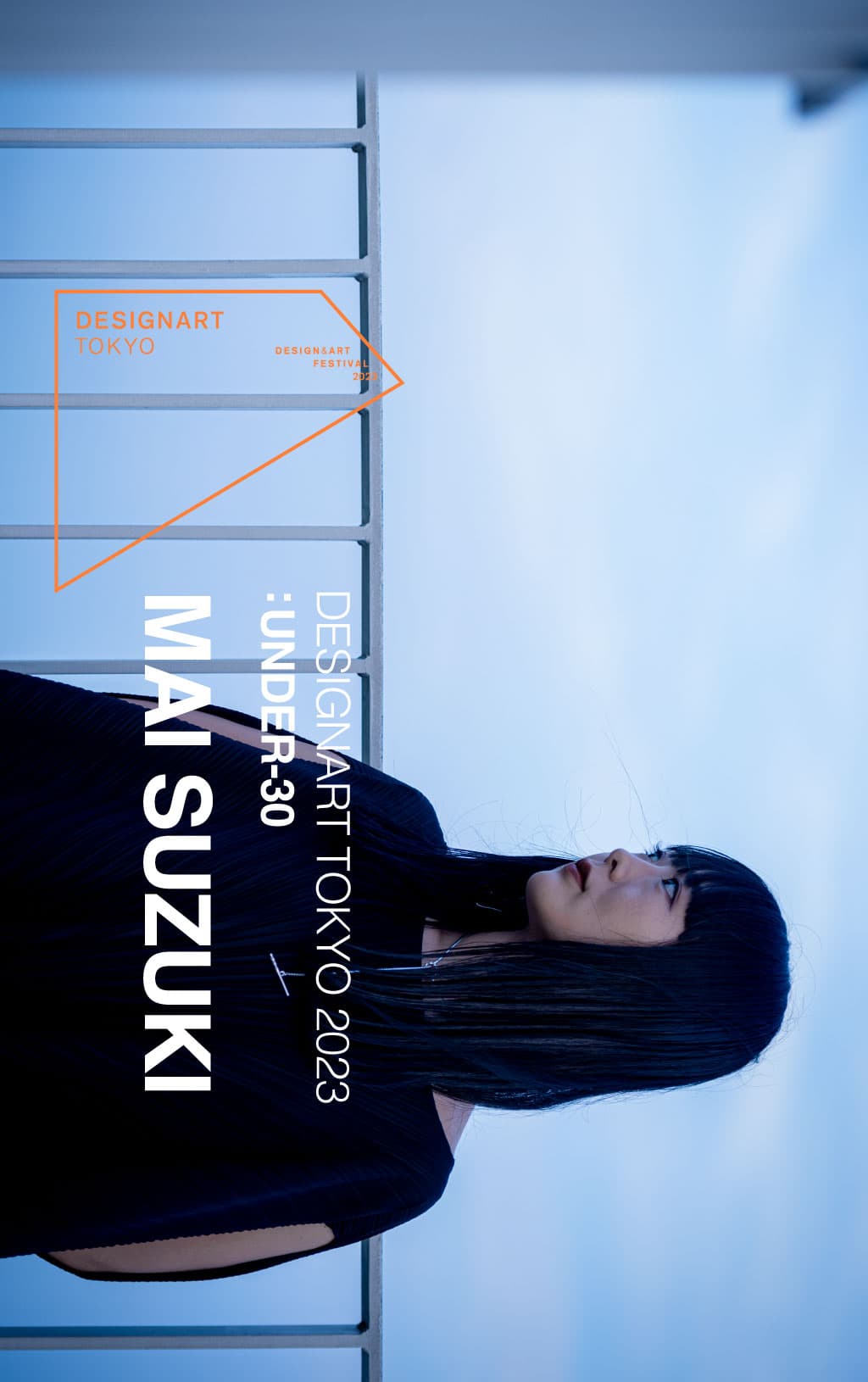時代感覚と感性が鋭く、既成概念にとらわれない発想力をもつユース世代。これに対して数々の修羅場を乗り越えて経験と知識を培ってきたベテラン世代。2つの世代の雄が互いにリスペクトを持ちながら、イーブンに時代を語ったら、どのような化学反応が生まれるか。新進気鋭のクリエイターや業界のレジェンド、有識者……誰もが知るあの人が今会いたい人は誰か。カルチャー、アート、ジェンダー、デザインなど多様な業界からの5組の稀有なディスカッションが実現。

今回登場するのはITジャーナリストとして知られ、時代の前哨を見守るオピニオンリーダーの林信行氏。その林氏が対談相手として選んだのは、以前仕事してから気になっていたという岩本涼氏。
裏千家茶道準教授で「宗涼」の名をもち、文化と芸術とビジネスを横断する異色の経営者だ。縮退しているともいわれる現在の日本の経済と文化の可能性に新しい光を当てる2人の提言に注目していこう。
岩本涼┃いわもと・りょう
1997年生まれ、26歳、早稲田大学政治経済学部卒業。茶道裏千家準教授。株式会社TeaRoom代表取締役。中川政七商店社外取締役。創業より静岡大河内地区にて日本茶工場を事業承継。農地所有適格法人株式会社THE CRAFT FARMを傘下に持ち、持続可能な茶生産体制の構築や、お茶の新たな需要開拓に努めている。「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2022」にも選出されたZ世代の起業家。
Instagram:
@ryoiwamoto11@TeaRoom
Twitter:
@ryoiwamoto1997
日本から生まれる必然性のない
ベンチャー企業と起業家
林:私は、1990年、岩本さんが生まれる前からテクノロジー系のジャーナリストとして仕事をしてきましたが、今思えば、「未来がどうなるか」ということにとても関心があったことに気づきます。
振り返れば、いわゆるパソコンが普及し、インターネットが広まり、スマートフォン革命があり……と取材してきて、いろいろな起業家に会い、スタートアップを見てきましたが、そのなかで違和感を持ったことがあります。それは日本の起業家たちの多くがシリコンバレーをとても崇拝し、それをモデルにしていたため、「日本から出てくる必然性がない企業」だったということでした。
言い換えれば、どこでも起業は可能で、もっと人件費の安い東南アジアの国などでやってもいい、日本でやる必要のないべンチャーを始める人がすごく多かったという違和感でした。

シリコンバレーで成功してきた人たちというのは、スティーブ・ジョブズも、イーロン・マスクも、日本に対して非常にリスペクトを持っていた。アメリカもヨーロッパも日本の文化にインスパイアもされたりもしている。
しかし、日本では日本の文化を切り捨てるようなべンチャーばかりが注目を集めてきた。人々の心に豊かさをもたらすと、世界からも注目されている日本文化をどうやったら未来に継承できるのかを考えさせられました。
やがて、新しいものだけを追い求めるのが未来をつくることではなく、過去の素晴らしいものを未来につなぐということも未来づくりのひとつだと気がつきました。そういう思いをずっと抱いていたなかで、若い世代でありながら日本の文化を武器にビジネスをしている岩本さんと出会ったことは衝撃で注目していました。
同年代の戦国武将たちと、
現代の利休、茶人起業家・岩本涼
岩本:ありがとうございます。私はいわゆるIT起業家でなく、テクノロジーが成し得ないジャンルでの仕事を立ち上げ、「日本の文化」に注目して、そこから新しい世代の企業の担い手に向けてスタートしたのですが、今の社会のニューリッチ、「新しい富の世代」が、そうした文化的なことを理解し、投資するためのきっかけをつくることができた思いました。

もともとはそうした若手の起業家たちとは接点がなかったのですが、たまたま裏千家に入門したことが契機となってその文化価値を彼らとつないでいきたいということで社会に出ました。テクノロジーやユースカルチャーと文脈がないというのはけっこうネックだったのですが、林さんたちが伝統文化の価値を若い世代に向けた語ってくれて助けられました。その林さんがテクノロジーの目線からどう伝統文化を捉えられているかというのが気になります。
林:実は、岩本さんご自身ではテクノロジーの軸を使っていないとおっしゃっていますが、周りにそういう人たちが多いし、Luupの創業者の岡井大輝さんと親しかったり。次の日本をつくっていくような経営層とかリーダーと繋がっていて、まるで戦国武将のなかに茶人・利休がいるようなイメージで岩本さんを見ています。
岩本:最近は多くの若手起業家と繋がっているように思いますね。ですが、新しい世代が世界に出ていかなくてはならないときに、日本の本質に触れる哲学を学ぶ機会がないことは課題だと思っています。
茶道の場合は、明治以降、礼法を学ぶ教育的なお茶になっていて、型、礼法、マナーを覚えるという点では確かに良いのですが、日本の思想哲学に触れるという観点が機能しなくなっていました。今、その文化に触れるためにお茶を学ぶ若手が茶室に集まるような時代になってきていると思っています。

仕事でアメリカやインドによく行くのですが、LAでは哲学サロンがオープンして若手の起業家たちが土曜日の夜に山にこもって対話しているのです。彼らと会話していると、成功している起業家でも、どのくらい儲けたか、どのゴールに到達したのか、という話でなく、「あなたはどういう人間で、どう考えるか」というような哲学的なテーマを話しています。
また、インドで今よく売れている本に『The Artist’s Way』という本がありますが、これは「リチュアル(儀礼)」と「スタジオ」という2つの言葉を生活内にどう取り入れていくかがテーマで、哲学的な問いに対してどう自分が向き合うかが書かれています。
このように新しい価値観や宗教すらも自分のなかにつくっていくような動きが海外では盛んに行われています。このムーブメントは20・30代にストレートに入ってきます。グローバル化によって自国と他文化を比較できるようになり、それを価値として復活させようと動きが重なって、皆さん学びを深めている現状だと思います。
林:お茶のような文化が、再び注目を集めていることについて思うのは、AIの時代になったとき、人間はそもそも何を生業にするのかを考えるようになることです。これから人間の関心はウェルビーングなども含めて、ますます自分の内面に向っていくと思っています。
そんなとき、茶の湯の文化は「日本にはこんなに素晴らしい文化があったんだ」と気づかせてくれる。それが世界に誇れるものでもあることを教えてくれます。
その点で、若き茶人・岩本さんは、日本の活動だけでもすごいのに、それを海外にも広めてくれていることにも心強さを感じます。
ラグジュアリー化した文化を
支えていくのは誰か
岩本:僕が問題視しているのは、20・30代の起業家たちが「文化」に対して時間とお金をかけて、投資をしてくれるということに対して、年長の富を成した世代からのそれを感じるきっかけが少なく、世代間の断絶を見ることがあります。冒頭に林さんが仰っていたようにテクノロジーに一点張りすることによって、文化との文脈を持っている起業家が少ないのかもしれません。
テクノロジーが成長し続けるのと同じように、世界に存在する多くのものは、必ず有形か無形かの資産に流れていくことのが自明の理で、機能が満たされた先には、文化的・精神的、そして無形な価値にシフトしていきます。
つまり、修練の先は誰も何もしなくてもラグジュアリー化していくはずなのです。
しかし、その一方で(茶の文化で言えば)裏側でその価値を支えていた宗家や茶室とかが、もう支えきれなくなっているのに、それを助ける層がいなくなってきています。ここは若手の資金源だけでは足りないので、そこをどう社会ムーブメント化していくかが重要な議論になります。
ビジネス界隈では、どう儲けるかという話にしかならないので、伝統工芸品とかがラグジュアリー化してどんどん世界に出ていくというのであれば、それはそれでいいのですが、それで民の暮らしのインフラをどう支えていくかも考えなくてはなりません。そこの議論が日本ではまだまだ足りないように感じます。

また、インバウンドで世界中から日本を訪れてくれるのはいいのですが、それがどれだけ自国に再投資されているのかという指標は絶対に注視しなくてはなりません。よく地域の課題として見られるのは、移住者や補助金で活性化しているように見えても、みんながスターバックスに入って打ち合わせをしてほとんどの利益はアメリカ本国に流れてしまう状態。地域で稼いだお金が国外に流失しているわけです。
地元の経済を豊かにしたいという考えであれば、すべてのサービスを地元企業が担い、そこに地元の人々の参画させるべきで、インバウンドの落とした金がそのまま地元に入って地元の経済基盤は安定するはず。
地方を活性化させるやり方でも、単にインバウンドを呼び込むという切り口では、せいぜいがラグジュアリー観光的な人寄せになってしまうのですが、それには違和感を感じます。伝統文化を残すためのモデルにはなっていない、この議論を深めたいですね。
林:そのあたり、実際には表層的で短期的な見方でやっていることが多いですね。

数百年間、為し得なかった
日本文化の「産業化」
岩本:実は、日本の残すべき文化というのは、一度も「産業化」されておらず、それが明治期に急に「産業化」するような社会の変化が起きたのがよくなかったのではないかと思います。そこはもう一回スクラップ・アンド・ビルドが必要なのではないかと。
例えば、銭湯も公衆衛生の観点で地主もしくは地域行政の補助を受けて立ち上がったものがほとんどです。入浴料金も「公衆浴場法」によって上限金額が決められていて、その代わり、補助金や助成金が支給されていたため、そもそも「産業化」するものではなかった。地震などの災害が起きたときに、疫病発生の対策として銭湯が地域のために利用される想定になっていました。
茶室も同じで、過去に信長や秀吉のような有力者が建て、そのままパトロンだけが変遷してきたもので、「産業化」はしていない。明治政府によって旧来のパトロンが退けられた後に、茶道の多くの団体は協会化して、会員数がKPI(重要業績評価指標)として重要になり、型を作って広め教授を増やし流布されていくことがより経済的効率化となった。

その結果、茶道の本質論からずれてしまったのではないか、というのが過去150年に起こったことです。
会員数を増やすのなら、タッチポイントを増やし、コンバージョンするためのカスタマージャーニーをつくれば難しくはないはずです。
そして、重要なことは次世代で誰がパトロンになるかを考えることです。一人ではなく、広義な意味での(複数の)パトロンに支えられる時代であること。私は「経済規模より経済効果」という言葉をよく言うのですが、経済効果を測ることが進んでできるような情報の透明性が出てくること。
この2つの組み合わせが大事なので、「より大勢の人たち」の協力によって「経済効果」を享受できるスキームができれば、そのモデルは茶道宗家なり、銭湯の会社なり、これまで果たされなかった「文化」をゆるやかに「産業化」することに近づけるのではないかと思います。
林:茶道の教室で、型を広めるという話が出ましたが、日本の義務教育も同じですね。KPIなど数字目標重視で、そこそこの品質の人間を大量生産する規模重視の教育になってしまっている。そもそも日本人の気質と、資本主義の相性はどうなのかと考えさせられます。

アメリカ型資本主義を日本が取り入れる度合いが大きくなればなるほど、日本はどんどん心が貧しくなり、不幸になっている割合が高まっているような気がします。だからといって資本主義の代わりがあるのかと言えば、ないのだけれど……。21世紀に入ってシェアリングエコノミーなど、新しい経済のあり方が度々話題になりますが、岩本さんはその辺りで何か感じていることはありますか。
岩本:まず、大前提として現在の資本主義の仕組みは、全世界の人口が減少に向かわない限りは変わらないと思っています。インドのベンチャー企業の社長と、いくら健康や無形資産の話をしていても「我々が欲しいのは、砂糖とカフェインと刺激だ」と言います。
産業革命でも、高度経済成長期でも、人々は砂糖をエネルギーとして飲んでいた。基本的に国が成長するとき、人々がハードに働いているとき、つらくても働かなくてはならないときには、夜でもカフェインを摂ってバリバリと働き続けます。国を成長させるという大義のなかで人間をフル稼働させるには、砂糖、カフェインなどの刺激が必要なのです。
ローカルとグローバルの間で
伝統文化は守れるのか
岩本:日本の文化が「産業化」していないのは大きな課題です。蔵づくりの文化の話で言えば、ほとんどの味噌蔵、醤油蔵は地域経済のための設置されたものです。たくさんの土地を持った地主がいて、酒蔵があって、景気のいいときは酒を造り、景気の悪いときは醤油を造る、ということで存続してきた。

今、こうしたほとんどの酒蔵が値段を上げられないというのは、そもそも地元流通で地元のためにつくっていたからで、新酒ができ次第に顧客に届けに行く、土地の生活に根ざしています。私が関わっているお茶もお酒と同じです。全国ほとんどどこでもお茶はつくれますし、それを地元の人たちに買ってもらっていた。そのために地元の賃金が上がらないような状況では値上げもできない。
ここに浮かび上がるのが、伝統文化における「ローカル(地元)とグローバル」の問題で、この2つ選択肢の間での苦悩があるのですが、将来的には地元と市場の両方を折衷していくべきなのが理想でしょう。
地元の伝統文化やそれを支えてきた地元企業の300〜400年の長い歴史はR&D(リサーチアンドディベロップメント)だった、そのことを自発的に伝えてくれる篤志のブランドマネージャーが出てくれば、何らかのスキームのもと、日本はもう一回資本主義のなかで戦える知財を示していけるのではないかとさえ思います。
西洋型資本主義をとった世界の国々では、アグリゲーションをひたすら続けることによって経済が発展しているかのように見せることをしていますが、このような表層的なやり方では、上前をはねることが行われているだけです。ホテルの予約サイトで言うなら、最終的に予約を受けているホテル側が利益を得ているかというとそうなっていません。

林:そうですね。上澄みのビジネスばかりが搾取を重ね利益を得ている。
岩本:レストラン業界で言うと、ダイレクトにファーマーと繋がるレストランやシェフは出てきてますが、その程度のことにとどまらず、例えば、あるカテゴリーでレストランを立ち上げるときも、いろんな知見や技術を取り込んだサービスを提供したいなら、料理の知識を深め、伝統文化のことも理解をもっと深める必要があります。
その意味で、世界的に有名なレストランのシェフは、和食の伝統文化の詳細を知ろうと、サンジェイ・インターナショナル(サンジルシ醸造)というアメリカにある醤油メーカーにある蔵を視察して、さらに学ぼうと麹工房を見に北陸とか愛知の蔵にも出かけていました。
日本が何百年もかけてつくってきた、蔵づくりに代表される技術は、蔵づくりに代表される伝統文化と技術は、定量的でなく定性的な話が多いので可視化しづらいので、全人類にとっても価値のあるこうした文化に「資本主義的な表現を与えること」が必要だと思います。
技術のR&Dを何百年も続けている日本の企業を英語でPRしながら、アウトプットとして出された製品を株式会社として商品化していくというのが日本の戦略になるだろうと思うのです。
ブランディング・コミュニケーションで、伝統技術のR&Dとプロセスも価値あるものとし、それにシステム化し、レベレッジを効かせて株式会社としてベンチャーを立ち上げる、これなら地元との折衷点も生まれ、伝統の技術を守ることもできるのではないかと。
林:確かに日本の伝統のものは、芸能にしても、言語化するのが難しく、そこから逃げてしまう傾向があると思います。そこをしっかりとやれば、世界に打って出ていける。
最近感心したのは、「SAKE ON AIR」というイベントで、世界中のバーテンダーやジャーナリストたちが日本酒の魅力とか、どうやったら日本酒が世界で認められるかという議論や提言をしていた2日間各十数時間におよぶオンラインサミットを見たことで、海外の人たちが日本酒についての言語化をしっかりしてくれていました。
こういうものがもっと増えたらいいですね。茶道のなかには日本文化のエッセンスが凝縮されていますから、それをテーマにやれば、いいプレゼンテーションの機会になり、伝えていく言葉も磨かれることでしょう。僕自身も若いときには、お茶とかにはそんなには興味はなくて歳をとってから分かってきたのですが。

「銭湯上がりにビールを飲めれば十分」
という暮らしのインフラ
──最後に、Beyond magazineからお二人に対して、日常を生きる私たちの疑問をぶつけてみた。円安が続き、海外に比べて賃金も安い。お二人の話を聞いていると希望もあるが、現実の若い世代のマジョリティは、「数年後の日本は…」と、シリアスな日常に直面していると思います。
林:そういうことに対しては国の動きに大きく期待したいと思っていますが、一方、熟年世代がどうあるべきかについてはJ・D・サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』の最後のシーンで、主人公のホールデンがなりたい人物像に近いです。その人物とは、丘で遊んでいて転げ落ちてくる子供たちを下で助けるのですが、何かの見返りを期待するわけでもなく、ただ見守っているだけなんです。そんな心に余裕のある上の世代が理想だと思っています。
実は日本マイクロソフトの創業に深く関わった古川亨さんもまったく同じことを言っていて驚きました。残念ながら最近の熟年世代の多くは自分のことしか見ておらず、そもそもあまり心に余裕がない。そこの部分の意識改革をしないといけないと責任を持ちつつ感じています。
岩本:今の若手の起業家は、同世代の苦しさを知っているのでみんなでサポートすると思います。世代間のギャップはありますが、若い世代はみんな新しい仕組みを考えています。
例えば、アルバイトの時給でも、これまでとは異なる店舗で働くときに最初の金額からスタートするのではなく、能力や過去の経験に応じて設定し、徐々に上げていくような試み、情報の透明化・可視化・スコア化も進めようという動きがあります。そのように少しずつ社会も滑らかになっていくのではないでしょうか。
それとお金がなくても良い生活環境になることがありうる。来年、原宿に銭湯が開業予定です。都心部でも、銭湯に入りビール一杯飲めればそれだけで十分に幸せではないか思うのですが、そこで問題なのは銭湯が「産業化」していないから経営破綻するという現実です。私たちは、こうした銭湯を支える座組みを新しい世代で考えています。
このように自分たちが大切にしている暮らしのインフラは自分たちで守るという人たちが私のまわりに出てきていますが、今後もそれは続いていくのではないでしょうか。

林:頼もしいですね。岩本さんの世代には本当に大きな期待をしています。ちゃんと日本の将来を見据えた熟年世代は、そうした人たちを邪魔から守って応援することなのかなと思います。
岩本:今の世代の特徴になることがほかにもあります。
例えば、“異世界転生”が可能になったこと。つまり、ありとあらゆるプラットフォームがあるので、個人がこれまでとは異なる新しい個性を持つことができ、それまでのキャリアを捨てても職業の選択が広がり、それが新たな経済圏につながっていきます。炎上した芸人でも新たなフィールドでユーチューバーとして活躍することができるということですね。
また、インフルエンサーの輝かしい生活を目標とすることは終わってきています。きれいに加工した写真の一瞬の「映え」よりも、短尺の動画で談笑しているゆるい風景を切り取った投稿した方が伸びがいいということ。
ネガティブに見ると、一枚の写真では物語を伝えられない言語能力になってしまったということですが、ポジティブに捉えると、ごく日常的な動画でもすごく豊かに見えうるということ。お金に変えられない価値が評価され、楽しまれるメディア環境になっていくのではないかなと思います。
大きな価値観の変化がない限り、「ハレの日」の活動は続かない。ハレの行事が日常化した例はほぼないのではないでしょうか。毎日サウナは無理だけど銭湯なら毎日でも行きたいというようなことです。
林:大阪に築55年の西田工業ビルというビルがあり、そこに「ハイパー縁側」という誰でも座れるスペースをつくったところ、とてもいい感じの公園のようになりましたが、地元の人たちがクラフトビールのブルワリーを開いて、これまでとは違う形で開発が進んでいます。
東大の横張真教授は「つくらない都市計画」を提唱されていますが、そういうものがもっとあっていいと思います。新しいもの、新しいテクノロジーをつくるだけが未来づくりではなく、古いものをどう活かすかということで、今日のお話につながってきたように思います。

Text:高橋正明
Photo:下城英悟
Edit:山田卓立