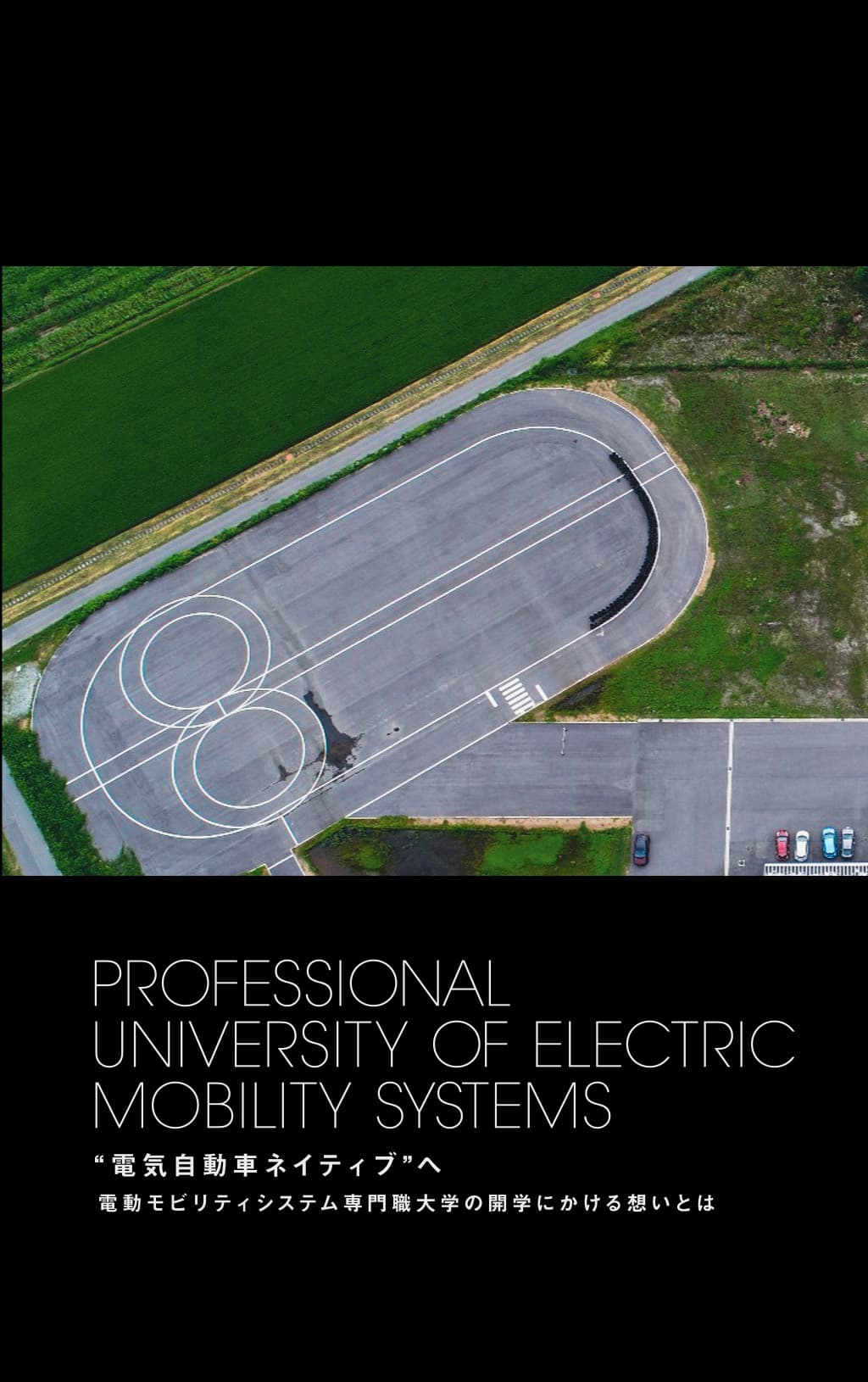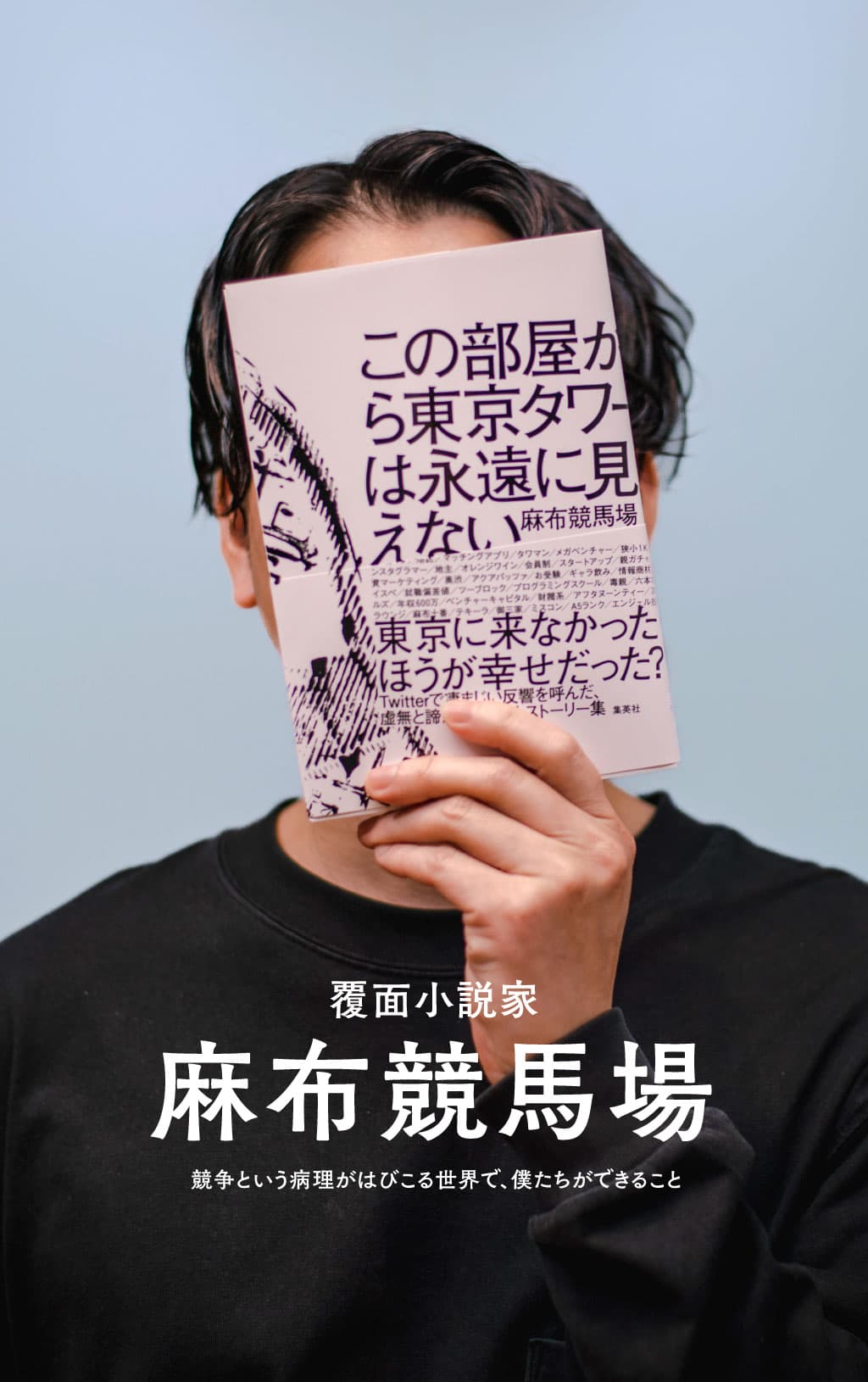“移動”という機能に特化したミニバンで育った僕らにとって、“走るのが楽しい”クルマなんてどこかフィクションのような存在。ゲームの中でスーパーカーを操ることは朝飯前だけれど、それはあくまでゲームの世界の話だった。でも実際に、100万円台から手が届く価格帯のホンダ「フィットRS」に乗ってみたら、掌の上で操れる感じが気持ちよくて、自分でクルマを運転して走ることの楽しさがわかった気がする。
ただの移動ではない、走りのモデル

僕自身、クルマ好きの両親の影響もあって、同世代の中では多少クルマ好きだという自負はあった。それでもやはり、移動手段としてのクルマではなく、自分で運転して走るのが楽しいクルマ=“走りのモデル”という概念すら、僕にはなかった。でも、ホンダ「フィットRS」を連れ出して、丸一日をともにした後、僕の中で“走りのモデル”と聞いて想起される概念が生まれたのだ。
前置きはほどほどにして、「フィットRS」の詳細を見ていこう。4代目となる「フィット」に“走りのモデル”である「RS」が加わったのは2022年10月7日のことだ。「フィット」が発売されてから、実に2年の月日が流れている。なぜこのタイミングかといえば、「RS」の開発手法として、レース活動から得た知見を元に“走りのモデル”を設計するという伝統があるから。
「走る」ということのイメージすら湧いてこない段階で、僕が試乗ステージに選んだのは軽井沢だ。当初、アマプラで配信されているアニメ『頭文字D 1st stage』の再生ボタンを押して、「走り」の予習をした段階では、赤城山にでも行こうかな? という軽い気持ちもあったが、主人公たちの走ることへのプライドを目の当たりにすると、果たして僕が赤城山に行って「走り」を語っていいのか? と疑念が湧いた。
ここはもう開き直って、クルマだからこそ行ける場所に行こう、と考えた。普段、友達とどこに行こうかと相談するときのように、スマホを片手にググるのはもちろん、Twitterやインスタのハッシュタグを使って、美味しいコーヒーが飲めて、ちょっと買い物もできて、秋の季節に行って快適な場所を探し出す。そうして、僕が選んだ目的地は軽井沢だった。都市部の混雑と高速道路がほどよくミックスされた上に、ワインディングロードまである、試乗ステージにもうってつけの道のりだ。
入念なデスクトップリサーチを終えて、いよいよ「フィットRS」を郊外に連れ出す。
脈々と受け継がれるRSの遺伝子
「RS」の系譜が始まったのは、初代「シビック」からである。同車が1972年に発売された2年後に、マイナーチェンジが施される際に新グレードとして「RS」が加わったことに端を発する。当時、北米でスペシャルティ・カーのブームが始まっていたこともあって、若者でも手が届く価格帯かつスポーティな乗り味のクルマとして、若い世代に支持されて人気を博した。当然、初代「フィット」が2001年に登場した際にも、マイナーチェンジ時に「RS」が登場するか噂されたものの、実際には2007年に2代目「フィット」にてRSが追加されるのを待たねばならなかった。
僕の理解では、ホンダの四輪車の歴史の中において、走りのモデルとして高い人気を誇るのがRSグレードだ。面白いことに、一般的には、“RS(=Racing Sports)”とはスポーティな走りを意識したクルマにつけられる名称だが、ホンダの“RS”は“Road Sailing”の略称で、長距離でのゆったりと快適な移動を意識した名称として掲げられている。
2020年7月に生産終了した「ジェイド」での実装以降、日本にて展開されているホンダの車種でこの二文字を冠するクルマはない。ときには、新型「シビック」のタイ仕様にて2021年に実装されたRSグレードをわざわざ輸入するマニアがいるほどの名作なのだ。
RSグレードとノーマルモデルの違いとしてわかりやすいのがスポーティネスを強調したエクステリア・デザインだ。

テールゲートスポイラーを搭載した空力に忠実なボディだけではなく、フロントからリアへ、サイドシルガーニッシュを通して直線的に入るブラックの塗装はキュッと締まった印象を与える。「暮らしのクルマ」とホンダが謳うイメージを残しながら、走りのクルマとしてのポテンシャルを感じさせる。




ドアを開けて、運転席に乗り込む。176cmと大柄な僕でも、チルト/テレスコピック機構を備えたステアリング・ホイールを適切に調整すれば正確なポジションを取れる。グッと支えてくれる頼もしいシートに身を預けて、右足を載せたアクセルを踏み込む。思いのほか力強い走り出しに、いい意味で期待が裏切られた。
最高出力123ps/最大トルク253Nmを生む電気モーターを組み合わせたハイブリッド機構を採用することにより、電気じかけならではの中低速域における厚みのあるトルクがスムーズな加速を実現する。
都心の雑踏を抜けて、軽井沢に向かって高速道路をひた走る。ホンダ自慢のe:HEVシステムでは、基本はモーターのみで静かに走りモーターが苦手な高速領域では、エンジンが直接駆動し効率良く走行する。ハイブリッド・モデルであっても、スポーティに走りたいシーンでは、モーター走行でありながらエンジン音がくっきりと伝わるのも走りを実感できる嬉しいポイントだ。
前マクファーソンストラット式、後トーションビーム式というサスペンション形式は、コンパクトカー向けのシンプルな設計だ。マクファーソンストラットやダブルウィッシュボーンという形式は独立懸架といって、乗り心地も確保しつつ、スポーティな乗り味にもなるように設計をしやすいのだけれど、トーションビームというリジット形式は、乗り心地の良さとスポーティな乗り味を両立するのが難しいらしい。
しかしながら、「フィットRS」では、スタビライザーにおけるロール剛性配分を見直し、大きくリア側のスプリングレートを上げたことで、スポーティな走りを実現しながらも、首都高の目地段差をいなすのもお手のものだ。さすが、「RS」の称号を冠するだけのことはある。
丁寧な機能が走る楽しさをサポートする
大泉JCTから関越自動車道の77.0kmの路線変更のない一本道に入る。やっと走りに集中できる、と左手をハンドルの横のDRIVEモードスイッチへ伸ばす。SPORTモードに切り替えてみると、傾きのある加速感がリズム良く訪れるのだ。右足を押し込むとリニアに駆動が応答し、加速フィールが全身に伝わる。

実際のところ、速度計の数値自体が爆発的に増えるわけではないものの、速度そのものに関係なくやってくる小気味よくキレのある加速サウンドは“走りの楽しさ”をダイレクトに伝えてくれる。
青い看板に軽井沢、と表示された。高速区間を抜けて下道に降り、峠道に向かって舵を切る。操舵をすると、適度なロールを許しながらも、ぐっと足を踏ん張って、コーナーに沿って気持ちよく鼻先を曲げてくれる。シャープな操舵フィールを感じながら、ステアリングホイール上にある減速セレクターに指をやり、しっかり減速した上でコーナーに進入していく。
滑りやすい路面に落ち葉が浮いた山道では、慎重に走る必要があるが、ステアリングホイールに伝わってくるインフォメーションが豊かで、僕の拙い運転スキルであっても、十二分に走りの魅力を感じられる。

ひとしきりドライブを楽しんだあと、インスタで見つけたカフェを探して小休止をとる。ガジェット好きの僕としては、クルマから離れるときでも、ホンダの新技術を体感できるのが嬉しい。ホンダのコネクテッド技術による「Honda CONNECT」のサービスのひとつ「Honda リモート操作」アプリケーションで外部からのインタラクトが可能だからだ。

昭和な喫茶店を探してみたり、今時なカフェでインスタ映えするスイーツの写真を撮ったり、アウトレットモールで買い物をして……と、はしゃぎすぎて少々疲れのある帰りの道も安心して運転できたのは、コンパクトカーといえども、安全機能が充実していたからだろう。
ホンダ車に共通の車線維持支援システム(LKAS)では、右へ逸脱したなら左、左へ逸脱したなら右、と振動しながら切るべき方向へのステアリング操作を支援する。今回のようにドライブを楽しんだ後の帰り道では特に、ふとした瞬間の事故防止につながる。

僕の生まれた2001年は、初代「フィット」の生まれた年でもある。オールインワンな1台として33年ぶりにトヨタ「カローラ」の販売台数を塗り替え、新たな時代の風を感じさせる代表的なハッチバックとなった「フィット」は、僕にとってF1事業と並んでホンダのアイコンでもあった。冒頭でも説明したように、レース活動からのフィードバックを量産車へと還元するRSグレードの、中でも「フィットRS」への試乗は僕にとっては“ホンダそのもの”を駆る旅でもあった。
人間はいつまで走り続けるのだろう。新幹線や飛行機の普及によって、とっくの昔に「速く移動すること」を機械任せにできるようになったのに、今でもオリンピックの目玉種目は100メートル走だ。0.1秒、ときには0.01秒を縮めるのに、人類の奇跡と進化の夢を見ている。同じように、自動運転が実現しようという現代でも、自らがコントロールしてクルマを自在に走らせることに憧れを持っている。そう、「走る楽しさ」を知ってしまった僕は、それから逃れることはできない。アスファルトを切りつけるあの感覚を思い出して、今日もまた、クルマのキーを手に取るのだ。
製品貸与:ホンダ